Leica Summarit M 50mm f1.5
Zeiss社が発表したかの有名なSonnar50mm-f1.5に対抗すべく、バルナックライカ用の 当時もっとも明るいレンズとして1949年に誕生したのが、このズマリットです。もともとはシュナイダー製のクセノンを母体とし、以降M型ライカ用のSummilux50/1.4へとバトンを渡すまで、約10年の間ライカのハイスピード標準レンズの座をつとめました。
黎明期のハイスピードレンズにありがちな開放時の甘い描写故、クセ玉の代表格とされ、評価する人間の主観によっては「悪玉」とも「銘玉」とも、その評価は極端で、中古相場も世相を反映して乱高下する非常に奇特なレンズです。
また、製造時期により多数のバリエーションが存在し、各々の保存条件や製造時のばらつきによっても描写性能が変化し、購入にはそれなりの覚悟を必要とします。 私の入手した個体も、購入時は中玉のコーティングが完全に劣化し、それによるフレアの オンパレードで、劣化が原因と解るまでは「う~ん、これがクセ玉の描写か」と 誤った見解を持ったほどでした。
しかしながら、大変優秀な技術を持っておられる某有名レンズ研究所にて、新たな命を吹き込まれたSummaritは当初の想像を遙かに超えた性能を発揮し、掛け替えのない一本へと復活したのです。
開放~f2.8程度までは微妙なソフト感をのこした独特の柔らかな描写をし、絹のベールを被せたかのような艶のある美しい画像を形成。f4以降急激に増す先鋭度は8あたりから、仕上がった原版をルーペで覗く目が痛むほどのシャープネスを発揮します。 開放から破綻のない優秀な性能を誇るSummicronを秀才に例えるなら、特定の条件における、撮影者の予測の範疇を越えた描写性能を持つこのSummaritはまさに「天才」の名を冠するレンズなのかもしれません。
ズマリットの所有欲を増す危険な描写。全体的にハロが目立つ独特なソフト描写になります。しかし、ルーペでポジを拡大するとしっかりと合焦部分は細部まで解像されています。ボケ像はややざわついた感じもありますが、この年代のハイスピードレンズとしてはまとまりの良い描写と感じます。
解放ではややソフト感が強いながらも、f4辺りから柔らかさと高いシャープネスが同居する独特の描写となります。再研磨+再コーティングのおかげでこの程度の光源ならばフレア・ゴーストの発生は見られません。
屋外でかなり強い太陽の反射をいれましたが、特に問題は無いようです。絞り込むと非常にシャープで繊細な描写となります。解放描写とのギャップが何とも言えず、オールドレンズならではの楽しみとなります。
M2以降のM型ライカで使用すると、50ミリのブライトフレームはフレームアウト部も確認しながらの撮影となります。M型ライカがスナップ撮影に好適とされる所以ともなります。同一被写体で同時に確認する術がないのですが、やはり、一眼レフとは一味違うフレーミングになるなぁ。と、感じています。
絞り込んだ時の、非常に高いシャープネスを実感できる一枚。画面全体に写る芝生の一本一本が綺麗に解像されています。逆光気味ですが、レンズフードの効果もあってコントラストの高い映像となりました。ちなみに純正フード「XOONS」はチリメン塗装された角形の美しい造形で、単体で一万円以上の値が付く人気アイテムの一つです。
35mmの画角が馴染んでいる自分にとって、50mmの画角はちょっとした望遠レンズ。気になった被写体を少しだけクローズアップする感覚は、M型ライカのブライトフレーム越しだとさらに強調されます。
バブル期に賑わったリゾート施設。現在では民家の倉庫となっていました。写真の「記録」という特性だけを考えればスマートフォンの存在は偉大ですが、自分がいまだカメラを手放していないのは、きっと写真の「それ以外の何か」に囚われているからなのでしょう。



















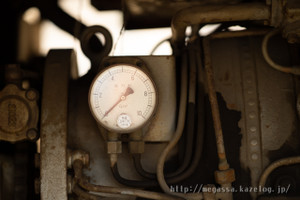



























最近のコメント