Zeiss Otus 55mm f1.4 ZF.2 (APO-Distagon)
50mm付近の焦点距離と解放f値1.4のスペックを持った単焦点レンズは、フイルム一眼レフの時代にほぼ全てのカメラメーカーから販売をされていました。135フォーマットフイルム(いわゆる35mmフルサイズ)において「標準レンズ」とも呼ばれるその焦点距離は、遠近感や画角が比較的人間の視覚に近い事に由来する癖の少ない描写特性を持つことに加え、解放f値の明るさ、適度な被写界深度、比較的短い最短撮影距離の特性から対応可能な撮影場面も多く、文字通りの「標準」として活躍しました。私の学んだ大学の授業では、1学年目の前期課題のほとんどはこの50mmだけを使用する縛りが与えられていたのですが、撮影の技術・理論の基礎習得にはとても有効な手段であったのだろうと今更ながらに感じています。
ところでこれら「標準レンズ」には、多くのユーザーにとって初めて手にする1本(いわば、そのメーカーの名刺的な役割)となるからこその大事な使命が存在しています。それは、十分な性能を適度な大きさと重量そして価格で提供されなければならないという事です。この二律、三律背反とも言える命題のため、標準レンズ設計の歴史を紐解くと結果としてはある種の最適解、総じて「変形ダブルガウスタイプ」と称される6群7枚の光学系へと導かれていったように感じます。かつて各社が公開していた50mm f1.4のレンズ構成図、そしてその描写特性に共通点が多い事からは、逆に「標準」であることの難しさを感じ取れるとも言えるのではないでしょうか。
さて、デジタル一眼が主流とっなた昨今、「標準」の役割を「標準ズームレンズ」へとバトンタッチしたかつての「単焦点レンズ」には、新たな時代がやってきたとも言えるでしょう。開放をf値を1.8としたことで安価となった単焦点レンズの入門モデルとして(いわゆる撒餌レンズ)、また解放f値を0.95やf1.2などとした明るさ・描写性能を極めたフラッグシップ的モデルとして様々な新レンズが登場しては話題に上っています。さらに「標準」の中でその代表を務めたと言ってもいい、解放f値1.4のモデルさえ「標準」に課せられたコストの枷が外された事もあるのか「6群7枚変形ダブルガウスタイプ」ではない新設計のレンズもお目見えするようになったのです。中でも「純正」よりも高額な定価設定で登場した「非純正」のSIGMA 50mm f1.4 DG Artや、当初40万円を超える売価でお目見えした本レンズには度肝をぬかれました。
Zeiss曰く「標準レンズにおける完璧の概念を塗り替えた」とした、全長140mm超、重量約1Kg、フィルター径77mmと、135mmクラスの大口径望遠レンズに匹敵する装いを有する本レンズは、百花繚乱ともいえる現行焦点距離50mm付近のレンズで、間違いなく究極の一本であると言えるでしょう。Zeiss標準レンズ伝統のPlanarに類する設計ではなく、広角レンズでの採用例が多いDistagonタイプ(いわゆるレトロフォーカスタイプ)による非球面レンズを含む10群12枚のレンズ構成は、なんとその半数が異常部分分散特性レンズで占められるという遠慮(?)の無さで、設計の概念すらも塗り替える勢いです。一眼レフの黎明期に良く見られた性能確保の手段同様に、焦点距離を僅か長めの55mmに設定した事からも、設計者の強いメッセージが伝わってきます。この塗り替えられた標準レンズの概念、拙い映像では伝えきれないその魅力を是非皆様の眼力で汲み取って頂ければ有難いのです。
f1.4。標準設定のJPEG撮って出しでこの色ノリです。もともと派手に彩色されたオブジェでしたが、どちらかと言えば派手目になるといわれる記憶の中の映像よりもさらにビビッドに感じます。開放描写で問題になる周辺光量落ちや口径食の影響も限りなく軽微でしょう。なによりボケた背景の切り株や庭石にもしっかりと立体感が宿っているのは一種不気味なほど。
丁度、恐竜オブジェの背びれがボケチャートとして役立ちました。距離に応じて徐々に大きくなるボケ像が確認できます。硬すぎず、柔らかすぎず、前後に均質に広がるボケ像、いい塩梅です。旧来の設計ですと口径食の影響もあって背景が同心円状に渦を巻いたように変形する通称グルグルボケが目立ちやすい状況ですが、本レンズでは当然目立ちませんよね。ピントの切れ込みも解放とは考えられないほどシャープです。
モノクロにすることで、トーンの繋がり、優れたコントラスト再現性が確認できます。高解像度センサーの恩恵もありますが、合焦部を拡大すると、オブジェ構成素材の結晶の粒を感じられるほどのシャープネスに驚きます。
さすがに多少の破綻を生じ「味わい」のある描写をするだろうと想像したピーカンの建造物。こんなに「普通」に写ってしまうとは。。。。。。周辺光量落ちはさすがに感じ取れますが、それ以外に突っ込む要素が見当たりません。描写のクセに頼れないレンズ、実力試験試をされている気もしなくはありません。
対称光学系を基本とした変形ガウスタイプのメリットに歪曲収差の補正が挙げられますが、レトロフォーカスタイプで設計された本レンズも非球面レンズや最新の設計技術を活用し、非常に高いレベルで補正がされています。デジタル補正の恩恵を得られない組み合わせでの利用ですが、歪曲の影響を実写で感じる事は殆ど無いかと思います。
かなり輝度差の大きい被写体でしたが、露出補正のみで飛びやつぶれの少ない映像を手に入れられました。部分補正をせずにこの仕上がりです。センサーのダイナミックレンジを生かし切る相当に懐の深いレンズだと感じます。
本来絞り込んで撮影するのが妥当な被写体ですが、機械精度も高くEVFでもマニュアルフォーカスによるピント合わせが快適なので、絞りを開けてファインダー像の変化をついつい楽しんでしまいます。フリンジの少なさもアピールポイントとされていますが、なるほどこんな光源下でもエッジに不用意な色づきは発生しません。太陽を避けたフレーミングにしてはいますが、逆光の耐性も当然高いレベルで確保されているとお知らせしておきます。















































































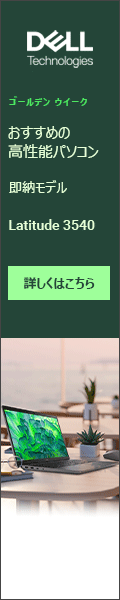



最近のコメント