ZOMZ(ザゴルスク光学機械工場製) ORION-15 28mm F6 (L39)
オールドレンズという言葉が耳に馴染んでからそれなりに時間が経ちましたが、デジタルカメラが一般化するより前に「旧ソビエト連邦や東独製レンズ」のブームが起こっていたと記憶しています。中心となったのはバルナックライカのマウントであるL39のスクリューマウントレンズ群で、バルナックライカを模倣したいわゆる「フェイク・ライカ」「コピー・ライカ」などのボディーと共に一部で人気を集めました。ライカ純正のレンズに比べて非常に安価に手に入れる事が出来た事も人気の一因ではありますが、それらはライカやZeissの光学設計をコピーした物も多く、その性能が価格以上に魅力的だった事が挙げられます。加えて、製造から長い期間が経っていたことや、素材・工作精度のバラつきが多い事なども重なって、とても「個性的」な描写をする製品や個体も多く、これが現代へと続く「オールドレンズ信仰」の発端のようなムーブメントになっていったのではないかとも想像しています。
さて、曲率の大きなメニスカス凸レンズ2枚を対象に配置し、画面平坦性の良さと歪曲の少なさから超広角レンズの元祖ともされたHypergon(ハイぺルゴン・ハイパーゴン・ヒパーゴン)は、極端な周辺減光特性がある為に、それを緩和するために露光中に回転させる「かざぐるま」をレンズ前面に配置したとてもユニークなレンズでした。そしてこのHypergonの凸レンズの内側に、やはり対称型にメニスカス凹レンズを配置し周辺減光を始めとした多くの欠点を解決すべくZeissによって製品化されたのが4群4枚対称構成のトポゴンとなります。ライカ判用としては、オリジナルのトポゴンの他ニコンやキヤノンでも25mmの広角レンズで採用(バックフォーカスが短いので、いずれもレンジファインダー用)されているものが有名ですが、本レンズ、ORION-15も焦点距離こそ28mmではありますが、立派なトポゴンタイプの広角レンズとなります。
「コピー」という言葉にはどことなく「本物ではない」というニュアンスが含まれている事もあってか、ORION-15=トポゴン-コピーなどと聞くと「あの」ウルトラマンや、「あの」ガンダムや、「あの」クレヨンしんちゃんなどを思い出してしまうのですが、ドイツ・ワイマール共和国時代の技術支援の賜との事ですので、立派なトポゴン-ファミリーとして安心して?レビューを進めたいと思います。
やはり、最初に驚いたのは中心部のシャープネスの高さです。撮影に試用したのがSONY製のα7 IIIと2,400万画素を超えるセンサー機種ですので、モニター上で悪戯に拡大を繰り返すとセンサーの解像度の方がレンズの解像度を超えているのはハッキリと分かるのですが、実際の映像から感じられるシャープネスには全く不満を覚えません。ライカ判のフイルムはデジタルで言う1,000万画素相当であるという話を鵜呑みにするのであれば、至極妥当なところでしょう。最新のデジタル対応レンズは、超1億画素をも想定した解像度で設計されているものもあり、そういった解像度の高いレンズを通した画像を見慣れていると、そればかりに注意が向いてしまいがちですが、映像から感じられるシャープ感はどうやら解像度のみによって決定される訳では無いのだろうと、改めて認識した次第です。
改良Hypergonのトポゴンタイプといっても、やはり解放絞りでは周辺減光が発生します。ですが、裏面照射型のセンサーを採用した7 IIIでは、初期のフルサイズデジタルで感じられた極端な周辺減光や大きな画像の乱れを感じる事は無く、むしろ適度に残存するそれらによって、非常に印象的な映像を提供してくれます。本レンズを覗くと、実際の口径から少し(1.5絞り程?)絞られた状態が「解放絞り」である F6になっている(参考:表題部の画像)事に気付きますが、これは残存収差と実際の画像のバランスを考えての設計なのかと合点がいきます。絞り込めば周辺の画質は徐々に改善し、深まる被写界深度も手伝ってとても端正な画像を形成します。しかし、実際のピント位置と被写界深度から感じるソレは、大きく違う事をMFアシストの拡大表示が示していますので、ピント調整にはしっかりと神経を使いたいものです。試写した日は日中雲に覆われる事が多く、低コントラストな状況で撮影するタイミングが多かったのですが、渋く優しめの発色や諧調の繋がりの良さなどは、本レンズの素性の良さが多分に影響しているに違いありません。古いレンズではありますが、構成枚数の少なさと非常に奥まった前玉位置によって、適度にハレ切りを行ってあげれば、逆光気味でも実用可能です。40.5mmと汎用性の高いフィルター径を採用していますが、フィルターを装着してしまうと絞りの操作が出来なくなる仕様の為に注意が必要です。もっとも解放の描写が非常に魅力的ですので、あえて絞りは F6に固定してフィルターやフードの装着してしまうのもストイックで良いかもしれません。
日常の撮影はマイクロ4/3機を愛用しており、多数のレンズを撮影に持ち込むスタイルの自分としては、携行物を肥大化させるフルサイズ機にはやや否定的な感情も持ち合わせておりますが、ORION-15をクロップ無しで使用したいと考えると、ミラーレスボディーの一台でもあった方が良いのかなぁ、と本気で考えだしてしまいました。とても悲しいことですが、執筆時点(2022年9月)でORION-15の故郷は戦争状態にあります。ロシアから届いたこの素敵なレンズを心の底から喜んで扱える日が、どうか1日も早く訪れますよう願わずにいられません。
本レンズの魅力が詰まった解放描写。対照型の利点である「歪曲収差の少なさ」や、中心部のシャープネスも見事の一言。戦前設計の広角レンズとは俄かには信じられません。そして周辺に向かって徐々に落ちてゆく光量と解像感が独特のリアリティーを感じさせます。人間の視界は本来は楕円形である事を考えると、周辺まで完璧に写し込んでしまう現代の映像の方がある種の虚構なのかもしれません。標準設定のままのJPEG撮って出しですが、コンクリート柱のハイライト部の立ち上がりを見るに、単なる眠い描写のオールドレンズではないことが分かります。
曇天の日陰ですからもともとコントラストは低い状況です。しかしながら、この優しい発色とトーン再現の素晴らしさはどうでしょう。4枚という少ない構成枚数と経年劣化の原因となる貼り合わせ面の無い構成のお蔭でしょうか、精密な水彩画を思い起こさせる描写がとても印象的です。
 長い期間製造されたレンズですので、太平洋戦争末期の遺構でもあるこのホッパー跡と同時期に生産された個体もあるのでしょう。大胆にアンダー側に露出を振っていますがシャドーの諧調が豊富なようで、ハイライト側にトーンが出始めるまで切り詰めてもしっかりと暗部が描かれます。
長い期間製造されたレンズですので、太平洋戦争末期の遺構でもあるこのホッパー跡と同時期に生産された個体もあるのでしょう。大胆にアンダー側に露出を振っていますがシャドーの諧調が豊富なようで、ハイライト側にトーンが出始めるまで切り詰めてもしっかりと暗部が描かれます。
無常観なんて大げさに言うつもりもないのですが、古いもの、朽ちて行くものには、どういう訳か自然とレンズを向けてしまいがちです。現代のレンズは複雑な電子制御機構などが多く搭載されている為、流行りの「持続可能」という視点で見ればとても脆弱な存在と言えます。構造的に単純なスクリューマウントのオールドレンズは、逆説的には流行の先端を行っているのかもしれません。
カメラ内蔵の基本設定でモノクロ化をしていますが、ブリーチバイパス処理をしたかのようなメタリックな質感となりました。こういったモノクロ画像を見ていると、ふたたび暗室に籠りたくなる衝動にかられますが、減少を続ける感材・薬品の種類と、反して高騰して行く価格に心を折られます。本当に銀塩写真のハードルが上がってしまったんですね。
絞り開放の描写が面白くて、ほぼ撮影中絞りを動かす事を忘れていました。シャドーの諧調が豊富なのは、こういったローキー表現には最高の相棒になります。
日中空を覆っていた雲が夕刻にまばらになってきました。思い切って空にカメラを向けましたが、思いのほか逆光耐性も高く安心しました。実際の風景はこれほどドラマチックな印象ではなかったのですが、ファインダーを覗くと写欲がみるみる湧いてきます。しかし、個人的にこれほどまで露出補正ダイヤルのマイナス側ばかりを使う撮影も珍しいものです。
なんと言う事もない石畳の歩道ですが、ORION-15の魔法にかかればこの通り。非常に思わせぶりな映像を作ってくれます。映像もさることながら撮影者にも魔法がかかってしまう様で、ライブラリのORION-15フォルダがみるみる肥大化して行きます。
ここ最近は1:1や4:3のアスペクト比を多用しているので、しばらくぶりに3:2(35mmフルサイズ)で撮影すると、その長辺の長さにちょっと戸惑っています。学生時代はこのアスペクト比の画像を8x10(写真六つ切り)にノートリミングでプリントして提出していたのが、なんだか懐かしいです。この位の逆光では、特に気を使わなくても大丈夫そうですね。
設計はカラー写真以前のレンズですが、カラーバランスの偏りは感じません。ホワイトバランスはオートを切ってありますが、少しブルー寄りな日陰の描写も自然です。どことなくコダクロームでの撮影結果を思い出す仕上がりが懐かしさを助長しますね。僅か映像に「銀」を感じるのはレンズの味なのか、映像エンジンの妙なのか、判断にはもう少し時間が必要ですね。



















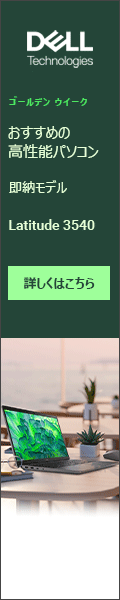



コメント