MINOLTA AF 35mm f1.4(G)
MINOLTA製Aマウント用の交換レンズは、モデル中盤に多くのレンズがマイナーチェンジ。
モダンな外装と幅広のピントリングを装備しましたが、そのうち一部の高価なモデルは、
結晶塗装風の外観とレンズ先端部へ金帯が施されるなど、特別仕様(G)タイプへ進化しました。
フルサイズで焦点距離35mmのレンズは、自身にとっては「標準画角」の感覚があって、過去から現在に渡り好んで利用している事を折に触れてはお伝えしてきました。著名な赤城センセー曰くのこの標準画角論?は年齢に伴って長焦点化する傾向があるのだそうで、年を重ねるごとに、より画角の狭い(年喰って視野が狭くなる、と自虐しておられます)長焦点のレンズに「標準」を感じる様になるとの事。実際自分に当てはめてみても、近頃は50mm、場合によっては85mm辺りの画角がしっくりする事も多かったりするので、なかなかに的を得ているような気もしています。もしかしてフルサイズでの焦点距離数と年齢がリンクしているのでは?なんて思うと、85mmがマッチするタイミングって相当体調悪かったのか?などど過去を振り返ったりもしてしまいます。
さておき、「迷ったら明るい方」を信条?とする筆者としては、35mmの中ではf1.4 のレンズがお気に入りです。ごく最近は f 1.2 の製品もちらほら出始めていますが、まだまだ個体数も少ないのでここは 買えなかった 気付かなかった事にしておきます。2025年5月の段階でSONY-Eマウント(フルサイズ)に対応する解放 f 1.4 のレンズの話をすると、FE 35mm f1.4 GM・FE 35mm f1.4 ZA が純正の新旧モデル。正式なラインセンス下で製造されている SIGMA製の 35mm f1.4 DG Art とその最新ミラーレス対応版 35mm f1.4 DG DN Art も忘れてはいけません。さらにLA-EA5併用前提でAマウントの製品を含めると、MINOLTA製のAF 35mm f1.4、その後継 AF 35mm f1.4(G)・SONY製へと移行したSAL35F14G・の3本がありますから、なかなかに豪勢なラインナップに。改めてレンズ(B級)グルメにとってのEマウント有用性が浮き彫りになった恰好です。
そんな数ある 35mm f1.4 ですが、少し前にMINOLTA時代の逸品 AF 35mm f1.4(G)を借用する機会に恵まれましたので、そちらを取り上げてみたいと思います。本レンズのオリジナルは、事実上、世界初のシステムAF一眼レフα7000(当然フイルムです)の登場から約2年後に、35mm f1.4 というスペックとしては、これもまた世界初のオートフォーカス対応レンズとしてお目見えしました。当時、35mmサイズ一眼レフ用の交換レンズとしてSummilux、Nikkor、Distagonなどが35mm f 1.4 マニュアルフォーカスレンズとして君臨する中、MINOLTA製品としてはこれまで f 1.8 止まりだった35mmレンズ待望の一本として披露されたのです。初代製品は研削非球面レンズを導入して光学的性能の向上を謳い、さらに広角レンズでありながらも、ボケ像へ配慮した9枚の絞り羽根による円形絞りを採用するなど、メーカー肝入りの一本でした。その後、他のMINOLTAレンズが新意匠とマニュアルフォーカス時の操作性を向上させる幅広のピントリングを採用した<New>タイプへと切り替えられる中で、本レンズも同様の刷新と非球面レンズの製造法の変更(研削>ガラスモールド)を受け、レンズラインナップ中で特別な一本である証(G)を授けられて誕生したのです。
時は既にズームレンズが台頭し、高額な広角単焦点レンズにとっては販売数を伸ばすのは難しい状況だったのは想像に難くありません。初代を含めても新品の販売本数はなかなか増えなかったのか、現在でも中古市場への流出は少なく、業界に身を置く自身にしてもそう滅多にお目にかかれないレンズとなりました。SONY製のデジタル一眼レフ用として、各種デジタル補正への自動対応を果たし、コーティングの見直しも図ったとされる最終バージョンの SAL35F14Gに至っては、お恥ずかしい話ながら中古商品を手に取った事が一度も無いという始末。中古相場の大幅な下落という憂き目をみたAマウントレンズ中、現在でもそこそこの価格で取引されるちょっとしたプレミアモデルとなっています。そんなかつての「英雄」(なんて言ったら怒られるか・・・)がいったどんな実力をもっていたのか、狭くなりかけた視野を目いっぱい広げてお伝えしてみようかと思います。
開放では、合焦中心部のシャープネスはそこそこ高い感じですが、ハイライト部分を中心にややフレアがかった柔らかい描写が特徴。画面周辺へ向けなだらかに光量・解像度共に落ち込む、いわゆるオールドレンズ然とした描写でしょうか。しかしながら破綻を感じるいやな癖ではなく、作風・作画意図によっては魅力的にも感じるでしょう。当時としては後発のレンズでしたのでその辺りのバランス取りが上手なのかもしれませんね。ちょっぴり樽型の歪曲が残っていますが、最新モデルだと自動で補正されるのか、機会があったら試してみたいですね。
新しいデジタル時代の35mm は f1.4の解放であっても、解放から相当にシャープネスが高く、こういった近代建築では硬質で冷たいイメージを伴って描写さがちですが、本レンズはその描写の緩さから、どこかしら温かみを帯び、コンクリートと言うよりは石造りの地下迷宮を撮影したような雰囲気でとらえてくれます。
にわか雨が止んだ後、戻った日差で濡れたアスファルトに落ちる街灯の影。開放では残存する色収差の影響で、本来グレーな筈のアスファルトに偽色らしきが色づきが見えます。恐らくはデジタル撮影の為により強調された結果なのだと思いますが、前ボケに赤・後ボケにブルーのフリンジが存在するのが、拡大画像からよくわかります。
絞りを5.6以上に絞り込むと、全域にわたってシャープネスが向上して、全体的にカチッとした描写へ変化します。繊細な合焦面というよりは、男性的でどっしりとした印象のピントの結び方です。解放付近の描写とは全く違う印象を受けるのもフイルム時代のハイスピードレンズにはよくある特徴です。
f2~4辺り、少しだけ絞った所が安心して柔らかい描写を楽しめる本レンズの「スイートスポット」といえるでしょうか。雨上がりの湿った空気感が心地よく描写されています。純正アダプターの併用でAFも作動しますが、作動音がせわしないAFより、じっくりとMFでピントを追い込むのがより相応しい使用法なのでは?なんて感じます。
画角の好みとは別に35mmが描く遠近感はとても心地よく、好んで使用する大きな理由です。5.6 くらいの絞りでシャープネスは一気に鋭くなります。周辺光量落ちも改善され、画面全体が隙の無い両像域で満たされます。
本レンズ、広角レンズとしては美しいボケ像を見せる事で当時高い評価を得ていました。若干の二線ボケは認められますが、ボケ像がガチャガチャとするほどのものでは無く、合焦部前後の広がりも自然。こういった被写体には解放の柔らかい描写が非常にマッチすると感じます。
フイルム時代の撮影感覚が忘れられない(新しい事を覚えない)ので、ホワイトバランスは太陽光に設定する事が殆ど。結果、「電球色」のLEDで照明された展示館では、色温度が低くアンバーに転んだ発色になります。本レンズ解放の柔らかな画質と色調の相乗効果もあって、全体的に優しい雰囲気を演出してくれます。
最短撮影距離は30cm。f 1.4としては頑張っていると評して良いのかと。かなり接近して撮影した一輪挿しは、幾何学模様がデザインされたクロスの上に置かれています。もっと汚らしく歪んだボケ像を想像しましたが、思いのほかまとまりの良い映像になりました。
開放では、短焦点とは言え少し離れたアウトフォーカス部の被写体に適度なボケが発生します。それによって独特の距離感・空気感が生まれてきますので、周囲の状況を取り入れるようなポートレートにも好適なのかもしれません。窓ガラスの格子部に少し揺らいだような特徴的なボケを形成しましたが、それもまた良いアクセントとなってくれました。




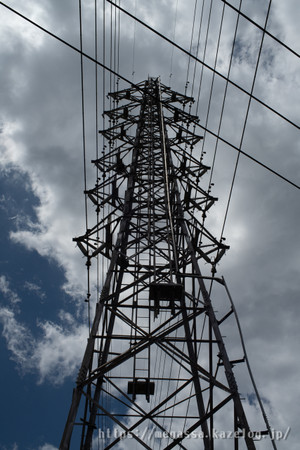



















コメント