M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO
「マイクロフォーサーズってボケないって言うじゃないですかぁー」
初めてカメラを購入するというお客様に、軽く、小さく、比較的懐にも優しいマイクロフォーサーズのカメラを選択肢として提案すると、結構な確率でこう否定されてしまいます。十二分に写りの良いスマートフォンを持ちながらも、あえてカメラを購入したいのだという動機の一つには「ボケを生かしたた写真を撮りたい」という目的がしっかりと存在しているのだという事を改めて強く感じますし、むしろスマホの画像とカメラの画像の決定的な違いは「ボケ」にあると思っている方も相当に多いのでしょう。「ボケないカメラだったらいらない」そういった結論が存在するのもなるほど頷けます。
この「マイクロフォーサーズ=ボケない」は言葉として分かり易い反面、重要な前提条件や枕詞が隠されている事に、カメラや写真の事を少し勉強すると気が付きます。「ピントを合わせた被写体までの距離が同じであり、且つ同一の画角・絞り値で撮影した場合」が前提であり、「より大型のセンサーを搭載した機種と比べると」という枕詞が続きます。仮に35ミリフルサイズ機で焦点距離50mmのレンズと同じ画角で撮影する為には、マイクロフォーサーズ機では25mmのレンズを用いる事になるのですが、「被写界深度」についての知識があれば、25mmは50mmよりも背景や前景がボケにくい事に気づくはず。(もちろん前述の通り被写体までの距離が同じで、且つ絞りが同じであれば・・・です)
なるほど「マイクロフォーサーズ=ボケない」は確かに正しい一面を表していますが、それは絶対的な事象ではなく、あくまで大型センサー機との比較による相対値。それがちゃんと伝えられていないが故、初心の方にさえバッサリと切り捨てられてしまうのは、なんだかもったいないなぁと思うのです。被写界深度に関する知識を身に着け、それなりの条件を揃えることができれば、「マイクロフォーサーズもボケる」のだという事を、我々のような販売に従事する者がしっかりと啓蒙していかなければならないなぁ、と改めて反省したりしなかったり・・・・・。
さて、被写界深度についての理解が進めば、マイクロフォーサーズの様な小型センサー機であっても、ボケを生かした撮影が可能となる条件をいくつか挙げることができるでしょう。「長い焦点距離のレンズ(いわゆる望遠レンズ)を使う」「被写体に近寄る」「ピントを合わせる被写体と背景や前景との距離を離す」そして「絞りを開けて撮影する」事です。前者の3条件は知識として持っていて損はありませんが、撮影条件や被写体の種類によって制限を受けますし、なんと言ってもフレーミングとの兼ね合いで実践できない場面も多いでしょう。結果、実際ボケを活用するには「絞りを開けて撮影する」事になるでしょう。これは解放f値の数字が小さいレンズを利用することでいつでも可能となる有効な手段ですから、小型センサーを採用している機種こそ、ズームレンズよりも明るいf値を持った単焦点レンズを入手することに大きな意味があるとも言えます。少々古い話になりますが、Panasonicが初期のマイクロフォーサーズ機GF1にキットレンズとして20mm f1.7という明るい単焦点レンズを採用していたのは、そういったメッセージも込められていたのでしょう。
当然、メーカー側もそれを意識しているハズ。OMDS(旧オリンパス)からは、描写性能・防塵防滴性能に力を入れたPROシリーズに属するレンズとして、解放f値を1.2とした17mm・25mm・45mmの3レンズを堂々ラインナップしています。1.4ではなく1.2としているのは、やはりボケへの拘りも相当に大きいのだろうと想像できます。とても興味深かったのは、焦点距離が違うこの3本の基本的な描写傾向がとても似通っている事です。当然画角は大きく違う訳ですが、仕上がった画像から共通の雰囲気が漂ってくるのです。デジタルに特化した新しい性能基準のレンズですから、解放から極めて解像度が高く繊細な描写を見せる反面、その解放では僅かにハロを伴う絶妙な柔らかさを持った優しい写りを見せます。一段絞るだけでこのハロは解消し、透明感の高いスッキリとした描写へ変化。f2.8辺りですでに解像度のピークへ達し回折の影響が出始めるf8辺りまで極上の解像感をともなったキレの良い画像を提供してくれます。肝心のボケ味もエッジ感の少ないとても素直なものとなり好印象です。被写界深度が深くなる17mmは、さすがにボケ自体は控えめになりますが、広角レンズにありがちなエッジが目立つガチャついたボケになる様子も無く率先して絞りを開けられます。
今回17mmを試用したことで、三兄弟、もとい三つ子のような印象を強く受けた1.2PROの三本。直販価格も全くの同価格(2025年現在税込み176,000円)と、決して安価とはいきませんが、全てを入手する価値もまた相当に大きいモノになるでしょう。冒頭、懐に(比較的)優しいと言った事を既に忘れているような発言ですが、OMDS製品としては、17mm・25mm・45mmのf1.8 (直販合計131,560円)シリーズが1.2PRO 一本分でお釣りも頂けますので、先ずはその辺から「決してボケないわけではないマイクロフォーサーズ」を是非とも体感してみて欲しいのです。
雨に濡れたクラシックカー。ハロを纏う独特の解放描写が高い湿度の空気と好マッチング。17mmという短い焦点距離なので、本来被写界深度はそれなりの広さ。しかし被写体にしっかりと寄り1.2という絞りを生かす事でボケを伴った一味違うスナップが可能になります。最短撮影距離は20cmと驚異的な数値。寄る事でさらに大きなボケを手に入れる事もできます。
解像度の高いレンズですが、無機質にならず程よい柔らかさを残した品のある描写をします。この辺りの雰囲気や素直なボケ味は25mmや45mmの1.2PROも同様の感想を抱きます。カメラ任せだとオートフォーカスの合焦点が思い通りになりにくい被写体ですが、フォーカスクラッチ機構を内蔵しているので、フォールディングをほぼ変えぬまま瞬時にマニュアルフォーカスへ切り替えが可能なのもシリーズ共通の利点。
1.2という解放を実現する為に、15枚ものガラスを組み合わせた非常に凝ったレンズ構成を持つ本レンズですが、前後のボケ方にも差異や癖が感じられないのでその解放描写を多くのシチュエーションで楽しめます。ボカす事にこだわった設計、そんなメッセージさえ受け取れるのです。
歳のせいか、最近はライカ判(24x35)や3:4の長方形フレーミングだと、この画角のレンズは少々広いと思う事が多くなった気がします。1:1にするとしっくりと来るので、17mmをカメラに付けた時は、スクエアフォーマットを多用しがちです。
1.2PROシリーズは、3本共に解放では少し柔らかめな描写をしますが、17mmにはその傾向がより顕著に表れている気がします。解像度は十分に高いながらも、湿度を伴った様な妖艶な描写です。周辺まで解像感は保たれるので、描写性能が落ちていると言うより、紗や弱いディフューズ系のフィルターを掛けたような印象になります。





















































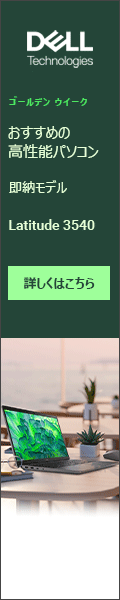



最近のコメント